引っ越しをきっかけにミニマリズムに目覚める方って、結構多いみたいです。かくいう私もそのひとり。
多分、「荷造り」を通じて、モノと正面から向き合わざるを得なくなるからじゃないかなーと。非日常感も手伝って、捨て活がはかどるのかもしれません。
そこで、「仮の引っ越し」を想定し、荷造りしながら捨て活するワークを考えてみました。
数十万円かけて引っ越さなくても今の家に住んだままできる方法ですし、実際にこれから引っ越す方が荷物を減らすのにも使えるような気がします。
私も持ちモノを見直したいときに実践している方法なので、ちょっと変かもしれませんがよかったら見ていってください。
「賃貸に住む人」
・30代一人暮らし
・不動産ライター
・元ハウスメーカー社員
…です。
会社員時代の転勤がきっかけでミニマリスト(自称)になり、生活費が月10万円以下に。
現在は会社を辞め、住宅・不動産関連のライター業で生計を立てつつ小さく暮らす日々。
「マイホームより賃貸」派。INFJ。
捨て活ワーク「引っ越し荷造り法」


捨て活ワーク「引っ越し荷造り法」は全9ステップ。
- マニュアル本を読む
- 理想の暮らしのイメージ資料を集める
- 引っ越し先の仮スペースを確保
- 荷造り用ダンボールを用意
- その日使ったモノを入れる
- 荷造りしたモノを確認
- 年間で使うモノを入れる
- 持って行かないなんてとんでもない!モノを入れる
- 引っ越さないモノたちとお別れ
ちょっと長く見えますが、準備段階が多く、実際に手を動かし始めるのはステップ5以降になります。
1.捨て活・片づけのマニュアル本を読む


まず、マニュアル本を読んで捨て活・片づけの全体像を把握します。
- どんな基準で捨てる・捨てないを判断するか
- どんな順番で捨て活するか
- どんな点がつまずきやすいのか
これを確認しておくのとしないのとでは、あとの捨て活の進み具合が変わってくるので。
捨て活・片づけ関係の本はたくさんありますが、根本的な考え方は似ているはずです。なので、自分に合いそうなものを1〜2冊ほど読んでみるといいかと。
ただ、「捨て活でこんな風に変わりました!」といった「終わったあとのこと」が重点的に書かれた本ではなく、具体的なノウハウが多い本がおすすめです。
2.理想の暮らしのイメージ資料を集める


次に、捨て活・片づけが成功したあとの「理想の暮らし」をイメージするための参考資料を集めます。
例えば、「丁寧な暮らし」「素朴だけどしあわせな小さな暮らし」が好きだという方は、
- 映画:かもめ食堂、リトルフォレスト
- YouTube:OKUDAIRABASEさん
- Instagram:石田ゆり子さん
- エッセイ:おづまりこさん
などを見てみたり。
何もない「ザ・ミニマリスト」な部屋が好きだという方は
- ミニマリスト佐々木典士さん
- ミニマリストしぶさん
- Minimalist Takeruさん
などの発信を見てみたり。
で、いいなーと思う画像やアイデアが見つかったら、以下のようなアプリを使って保存しておきます(得意な方はアナログのイラストやコラージュでもめちゃいい)。
ある程度素材が集まると、これがいわゆる「ビジョンボード」になります。
これ、単なるモチベアップとか「引き寄せ」みたいなスピリチュアル的なワークとかではありません。
というのも、捨て活・片づけを進めている最中は、今持っているモノや今の部屋の状態にどうしても引っ張られやすくなるんですね。
で、その状態でモノを取捨選択したり買い替えたりすると、「あれ?片づけ前からあまり変わってない…」ってことに陥りがち…
なので、「目標としているこの人の部屋にはこんなモノ多分ないだろうなー」「住みたい部屋のテイストに合わないなー」と客観的に判断するための手元資料をつくっておきたいんです。


ド派手な色・柄物出てきたらヤダな…とか。
完璧なビジョンボードをつくろうとするとキリがないと思うので、パッとみたときに「あ…いい…」「こういうの好きだわー」ってなればOK。
ハマりすぎず、次に進みましょう。
3.引っ越し先の仮スペースを確保
ステップ1〜2で頭のなかの準備が整ったと思うので、次は実際に捨て活・片づけに入るための物理的な準備です。
「引っ越しモード」のスイッチを入れるために、仮の新居となるスペースを確保します。
といっても、最低限荷造り用のダンボール1〜2箱が置ける場所があればOK。あとは、頭のなかで空っぽの新居をイメージします。


(怪しい暗示)
要は、場所の大きさに関わらず、新居のように「新しくキレイ」で「不用品を持ち込みたくない」ような、聖域を確保したいのです。
今住んでいる家・部屋に初めてやってきたときの写真が残っていれば、近くに置いて「今からここにもう一度入居し直す」とイメージしてみるのもいいですね。
実際に引っ越す方は、ぜひ引っ越し先の写真や間取り図などを手元に用意してみてください。
4.引っ越し荷造り用のダンボールを用意


続いて、実際に荷造り用の空のダンボール箱を用意します(宅急便の空き箱でもOK)。
「引っ越さないのにわざわざ用意するのは面倒…」って方は、キャリーケースや旅行カバン、何かほかの空のケースでもいいと思います。
ただ、
「元の棚やクローゼットから1回出して戻すだけ」はおすすめできません…。
多分、今の状態に引っ張られてしまって、「そこにおさまっていたようなモノ(似たようなモノ)」を選びやすくなるので(経験談)。
引っ越しで捨て活が進みやすいのは、
- 今の状態に関係なく
- 戻すときの細かい収納・配置を気にせず
に、単純に目の前にあるモノを「持って行く・持って行かない」で判断できるから。
ダンボールやキャリーケースに詰めるだけで非日常感が出てちょっとテンションも上がるので、個人的には用意してほしいなー…なんて…。
5.引っ越し荷造り1|その日使ったモノを入れる
さて、いよいよ「引っ越し荷造り法」での捨て活をスタートします。
やることは単純で、
朝目が覚めてから夜ベッドに入るまでに
「手に取ったモノ(使ったモノ)」を
ダンボール(or用意した入れ物)に詰める
です。
例えばこんな感じ。
- 洗面
→歯磨きセット、洗顔セット、ドライヤー、ブラシ、タオル - 保湿
→スキンケアセット - トイレ
→トイレットペーパー、タオル - 着替え
→下着、上下服、靴下、ハンカチ、靴 - 外出用身支度
→メイク用品、アクセサリー、香水
- 洗面(手洗い・うがい)
→ハンドソープ、うがい薬(使っていれば) - 入浴
→シャンプーセット、バスタオル、部屋着 - 保湿
→スキンケアセット - 洗濯
→洗剤、洗濯用ネット - 夕食
→調理道具、食器、洗剤、スポンジ、タオル - 歯磨き
→歯磨きセット - 就寝
→枕、布団、シーツ、アロマ、充電器類
ポイントは、衣服「類」やメイク「ポーチ」といった枠で入れるのではなく、「その日使ったモノ(手に取ったり身につけたモノ)」だけを入れるという点。
メイクポーチの底にまったく使っていないモノが入っているなんてこと、あるあるなので…
濡れそうな洗面用品とかトイレットペーパーなどの消耗品とか、面倒だったり箱に入れにくいモノは写真かキーワードでメモに残せばOKです。(布団とか大きすぎて入りませんし。)


次の日のコーディネートを入れるといいと思います。
タオル類も替えでOK。
- 鏡
- 洗濯機
- 冷蔵庫、電子レンジ
- テーブル、椅子、ベッド、棚
といった「簡単に動かせないけど引っ越すなら持って行くモノ」も忘れずメモします。
6.荷造りしたモノを確認
1日お疲れさまでした。さて、一息ついたら、荷造りした(とりあえず放り込んでいった)ダンボール箱とメモしたリストをのぞいてみます。
そこにあるのが、
1日生活するのに必要な最低限のモノ
です。
…どうでしょうか。思ったより少ないのでは…?
早速、仮の新居スペースに移動…といきたいところですが、その前に
本当に新居に持って行きたいかどうか
(ときめく・お気に入りかどうか)
をチェックです。
多分、「なんとなく使いやすいから」「ただ持っていたから」というモノが結構含まれているかと。
そこで、ステップ2でつくったビジョンボードを片手に、連れて行くモノを厳選。
買い替えたいモノがあれば、とりあえずAmazonや楽天市場のお気に入りに保存したり、「ほしいモノリスト」に書いておきます。
というのも、すぐポチるとかなりの確率で後悔するからです(経験談)。
必ず「捨て活を終わらせる→不足したモノを買う」の順番で。
無事に選び終えたら、持って行きたいモノだけを引っ越し先のスペース(聖域)に移動させます。
※この時点でダンボール箱に入れない(買い替えたい)モノも、そのまま残しておきます。処分するのは選別作業をすべて終えてからまとめて、です。
7.引っ越し荷造り2|年間で使うモノを入れる
たった1日で使うモノ・使わないモノを判断するのはさすがに無理があるので、今度は「1週間」「1ヵ月」「1年」単位で同じことを繰り返します。
例えば、1週間〜1ヵ月単位で使うモノといえばこんな感じ↓
- 衣類・リネン類
1週間分の替え - 掃除関係
トイレ掃除用品、部屋の掃除用品、ゴミ袋 - 調理道具・食器類
週末の鍋道具セットや作り置き用タッパなど - 趣味関係(休みの日に使うモノ)
キャンプ道具、習い事用品、推し活用品など
年間で使うモノは、主な祝日・イベントで考えるとイメージしやすいかもしれません。
- 1月:お正月
- 2月:節分、バレンタインデー
- 3月:ひな祭り、春休み、年度末
- 4月:花見、新年度・新学期
- 5月:ゴールデンウィーク、母の日
- 6月:父の日
- 7月:七夕、夏休み
- 8月:お盆、花火
- 9月:シルバーウィーク
- 10月:ハロウィン
- 11月:七五三
- 12月:冬休み、クリスマス、年末
年末の大掃除だけ使うモノとか、お子さんがいる方は行事用のお弁当用品や季節の飾り付け用品などがあるでしょうか。
ただ、1週間程度なら1日Ver.と同じようにできるかもしれませんが、1年間このワークを続けるのは私もヤです。
なので、
今回は頭のなかで去年の自分の動きを早送り再生し、そのときに戻ったつもりになって実際に使ったモノ(手に取ったであろうモノ)をダンボール箱に入れていきます。
1日Ver.である程度要領はつかめたと思いますし、年間で見てもいつもと大きく違う動きをする日って意外と少ないので、思ったより早く終わるかもしれません。
ただ、はたから見るとかなり怪しいので、家族など同居人がいる方は事前に説明しておくことをおすすめします…。
また、あとから見直しやすいように、1日Ver.で荷造りした箱とは分けておいたほうがいいかと。
なお、ここでも「多分使うだろうなー」「買ったときにセットになってたから…」といった理由で持ち物を入れてしまわないよう注意です。
入れるのは、あくまで「本当に使うモノ」だけ。
※シリーズモノなどの「揃っていることで真価を発揮するモノ・テンションが上がるモノ」は別です。
ひと通り終わったら、こちらも「新居に持って行きたいか」を問いかけつつさらに厳選し、新居スペース(仮)に引っ越しです。


(怪しい暗示2度目)
本当にそれ、持って行きますか…?
面倒ですが、ダンボールの中から取り出して使って戻す…が理想です。
やってられないよ!って場合は、写真に撮って元の場所に戻す…が現実的かと。
ただ、「自分が残すと決めたモノ」がどんな系統かを把握したいので、できれば近い場所に固めて置いてほしいなー…と…。
8.引っ越し荷造り3|持って行かないなんてとんでもない!モノを入れる
以上、ステップ7までで1年間暮らすために必要なモノの荷造りは終わりました。
じゃああとは全捨て…というわけにもいかないはず。なぜなら、手に触れていないけれど、実用的じゃないけれど、大事にしているモノってあるからです。
そこで、ここからは残されたモノをこんまりメソッド※で選別していきます。
- 衣類
- 本
- 書類
- 小物類
- 思い出品
この順番でモノを一旦集め、一つひとつ手に取りながらときめくモノだけを新居スペース(仮)へ移動、です。
※ほかの捨て活・片づけ本を参考にしている場合はそちらのメソッドでOK
ただし、前提として、これから見ていくのは「引っ越しで持って行かなくても生活に困らない」モノ。ここで選ばれなければお別れです。
そう思うと、「そんな…コレがない生活なんて考えられない…!」ってモノはすぐ分かるんじゃないでしょうか。


多分、それがこんまりさんがいうところの「ときめき」です。もし迷ったら、ビジョンボードと、聖域にある選ばれしモノたちを見てみてください。
9.引っ越さないモノたちとお別れ
ステップ8を終えた時点でダンボール箱やリストに入らなかったモノ…残念ながら、今、そしてこれから必要になることはないかと思います。
感謝の気持ちを伝えつつ、お別れです。
手放してスッキリ家が片づいたら、荷造りしたダンボール箱を持ち帰って(多分数歩戻るだけ)、荷解きして完了…。本当にお疲れさまでした。


主な持ち物はほぼトランク1つ分になります(極端)
あ、そういえば、ステップ5〜8までの間に買い替えたいモノをリスト化する過程がありました。
私の場合、金銭的に余裕があれば捨て活を終えた段階で実際に買い替えますが、難しければとりあえず古いモノを使って生活します。
ただ、手元にほしいモノリストがあることで「いつか理想のアレと置き換えるから…」という気持ちになるので、古いモノが残っていても無駄づかいしたりモノが増えたり(リバウンド)しにくくなるみたいです。
ちなみに、捨て活・片づけで一番難易度が高いのは何気に最後の「不用品を処分」するところ…。別記事にまとめてみたのでよかったらご覧ください↓
まとめ
以上、ミニマリスト流捨て活ワーク「引っ越し荷造り法」のご紹介でした。
好き勝手自己満足で書いたので、うっかり読んでしまった方は、変な人だなーくらいに気楽に受け流していただけるとありがたいです。
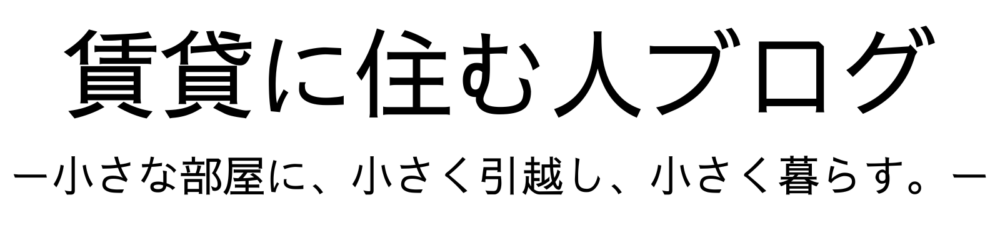
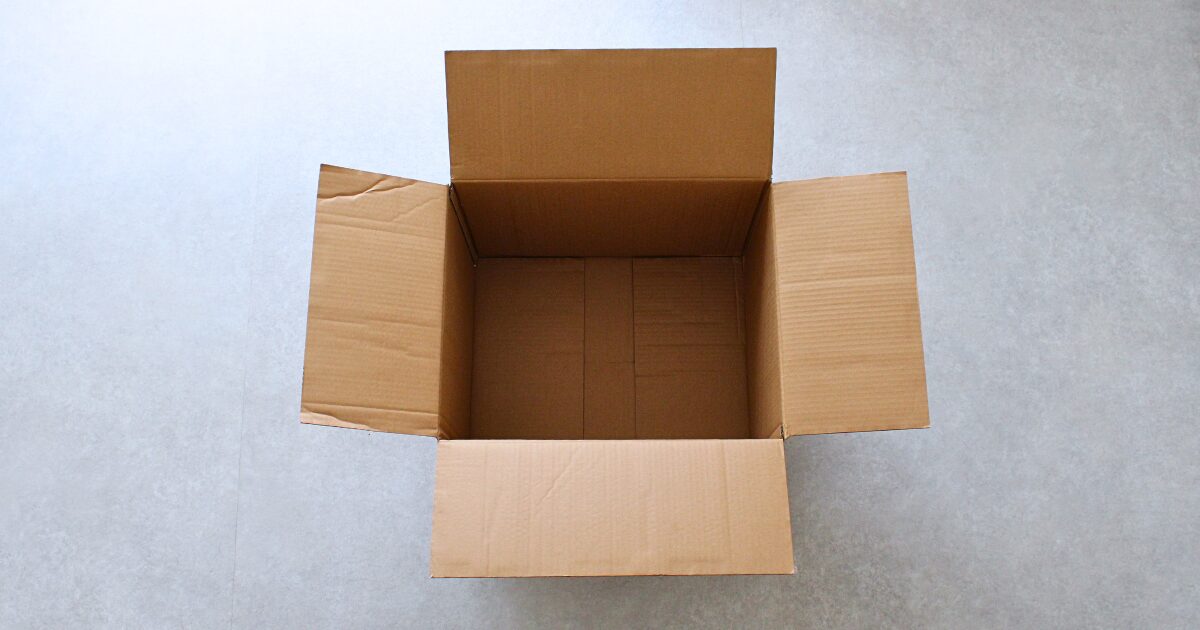







コメント